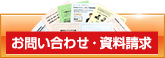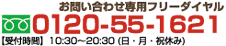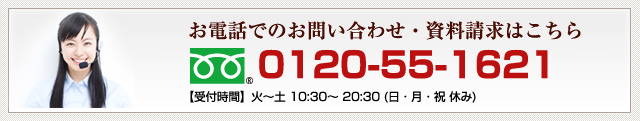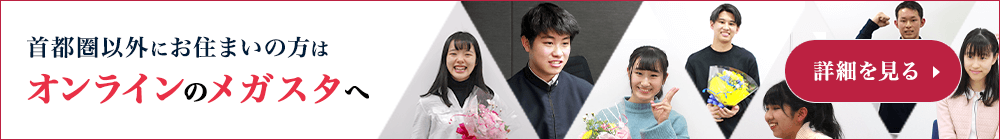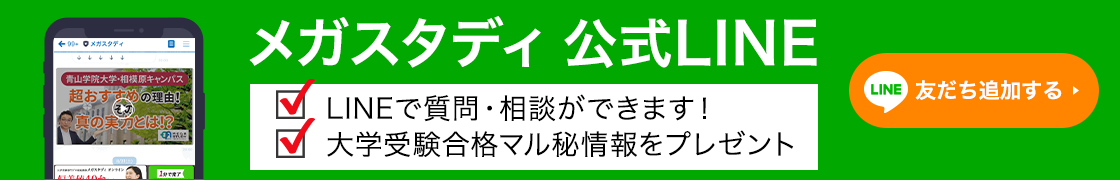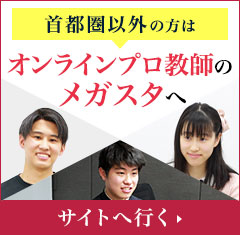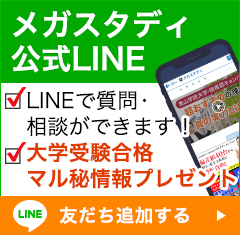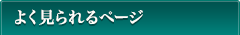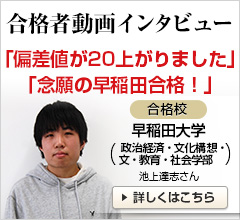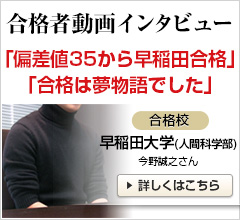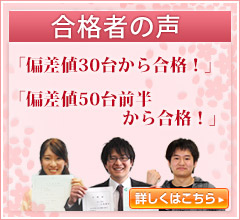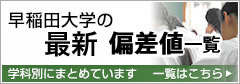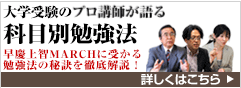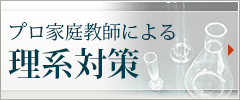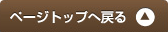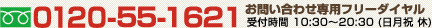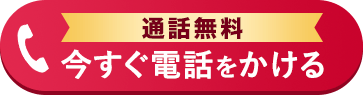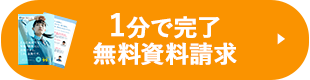早稲田大学
文学部
日本史 入試傾向と対策ポイント
偏差値40から早稲田大学に合格させます!
私大受験専門・家庭教師メガスタディが入試傾向を徹底解説!

このページでは、早稲田大学 文学部の日本史入試問題の「傾向と対策ポイント」を解説しています。
早稲田大学の文学部を目指す方には日本史入試の合格のヒントがきっとありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
早稲田大学 文学部 日本史の入試傾向
大問6題。小問45問。選択6割、記述4割。
全体的に標準的な問題が多く、難問は1割程度
設問は正誤判定を中心に、一行問題・空欄補充・年代配列も出題
正誤判定→2つ解答させるケ−スもある
全時代から出題
原始(15%) 古墳から平安(20%) 鎌倉から室町(17%) 近世(安土桃山~江戸)(22%) 近代(明治~第二次世界大戦)(22%) 近現代(第二次世界大戦~)(4%)、時代別にみると江戸(20%) 室町・安土桃山時代(13%) 縄文時代・飛鳥時代がともに(11%)の順
早稲田大学 文学部 日本史の対策
基礎の対策で9割を目指す
教科書レベルの基本事項を正確に理解するようにする。
全体的に標準的な問題が多く、難問は1割程度のため、教科書レベルの基本事項を正確に理解するようにして下さい。
時代・分野と幅広く出されるので苦手な分野を作らないようにする
記述では正確な漢字が書けることが大切
文化史の学習に重点を置くようにする。
図版を利用した問題も多いので、図説で美術作品を確認するように。
同じ内容の出題がみられるため、過去問を解くことが大切
早稲田の文学部の日本史は、全体的に平易な問題が多く、難問といえるのは1割程度です。まずは教科書を使っての基礎固めが重要になってきます。 基本的な問題で失点することがないよう、正確な知識を身につけるようにして下さい。用語集やサブノートを併用し、 重要用語の意味や事件が起こった背景・結果などを正確に把握しましょう。 また、重要用語などは手を動かして覚え、漢字表記の書き間違えがないようにしていって下さい。
苦手分野を作らないようにする
早稲田の文学部の日本史は、古代史に重点が置かれたり、江戸時代が必出であったりと、ある程度近代前史への偏りは見られますが、出題は全範囲にわたっています。不得意な時代・分野は残さないようにしたい所です。自分の苦手分野を把握し、分野別・テーマ別など的を絞って学習すると、効率良く苦手を克服できます。
正誤問題は選択肢の出題パターンを覚える
早稲田の文学部の日本史は、基本的な知識が身についていれば解けるとは言え、正誤問題はかなり細かい知識が必要となってきます。 単純に単語や重要用語を覚えているだけでは対処ができず、歴史の流れを細かく理解しておかなくてはいけません。 サブノートなどを利用して流れをつかみ、正しく詳しい知識を身につけるために、用語集や一問一答集を使って学習を進めて下さい。
また、過去問を解くことで、正誤問題の形式に慣れ、どういうポイントが誤文になるのかなど傾向を掴むようにしましょう。最初のうちは、選択肢一つ一つに対し「正しいか」「誤っているか」を、メモを取りながら細かく確認するのも対策の一つです。時間はかかりますが、確実に力になります。用語集や教科書を見直しつつ、取り組んでみてください。そのうちに、どこが狙われるポイントなのか、パターンが見えてくるはずです。
また、正誤文判定の問題形式に慣れるため、センター試験の過去問で肩慣らしをしてみるのも良いでしょう。
文化史・史料問題などの対策も忘れない
早稲田の文学部の日本史では、文化史が必出になっています。通史に重点を置いていると、文化史の分野がおろそかになりがちなので、要注意です。 図説・資料集は必ず何度も読み返し、美術品(仏像・建築物・絵画等)は名称だけでなく、外観も把握するようにして下さい。
また、日本史に関するニュースが、試験の題材になることがあります。日本史関連のニュースにはアンテナを張り、しっかり整理しておいて下さい。
史料問題は近年出題されていませんが、念のため、山川出版社の『詳説日本史史料集』には目を通しておきましょう。
まずは無料の資料請求、学習相談を
家庭教師のメガスタディには、早稲田大学・文学部に高い合格実績を出しているトッププロ家庭教師が多数在籍しています。
少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ無料の資料をご請求ください。お急ぎの方はお電話ください。
また、早稲田大学・文学部に詳しい教務スタッフによる無料の学習相談も承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどうやって受かるかをご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
◀ 早稲田大学文学部の他の教科も確認する