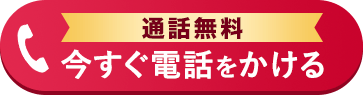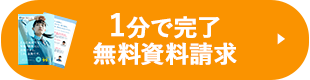これだけは知っておきたい!
私大受験に勝てる!高2・1月の勉強法まとめ
このページでは、高2の皆さんに「これだけは知って欲しい!」という勉強法などの役立つ情報をまとめています。
私大受験を考えている高校2年生には役立つ内容ですのでぜひ参考にしてください。
1.志望校に現役合格できる
スケジュールとは?
高2の方は、この冬から受験を意識した勉強を始めようと考えているかもしれません。
ただ、早稲田・慶應・上智・GMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)などの上位私立大学の入試は、「遅くとも高2の冬から受験勉強を始めなければならない」とよく言われます。
理由は、受験本番までの今後のスケジュールを考えてみると分かります。
高2の冬までで英語・数学・国語の基礎を固める
↓
高3の夏休み前に、理科・社会を固める。
↓
夏休み以降、応用問題の演習に入る
↓
志望校対策に取り組む
直前期は、本格的に受験勉強を始めるのが遅いと、第一志望(学部)の対策だけで、併願校(学部)の対策まで手が回らなくなります。また、大学ごとに入試傾向は違うため、偏差値が届いていたとしても、志望校対策をしていない大学の入試の点数はなかなかとれません。結果、第一志望に手が届かないと、どの大学も合格できなかった、ということになってしまいます。
「遅くとも、高2の冬から本格的に受験勉強を始めるべき」という意味が、お分かりいただけたでしょうか。
それでは、ここからは何をすればいいかをお話しします。
1月は、次の3つを押さえておきましょう。
2.1月の勉強 3つのポイント
ここでは、全科目的な1月に行う勉強のポイントを、3つお話しします。
①何よりも優先して徹底すべきこと
1月を含め、冬は暗記を徹底的に行う必要があります。
単語や用語、公式は早いうちに覚えましょう。
早いうちに覚えていれば、学校授業や宿題で問題演習をする時にその単語や用語、公式を自分で思いだして使う練習ができます。

定着の為、何回も繰り返す
具体例を挙げると、ある単語を覚えた際、覚える時期が早ければ早いほど、長文の途中、問題などで出会う回数は多くなります。回数が多ければ多いほど、きちんと暗記ができ、定着します。
また、数学の公式などはただ暗記するだけでは、使えません。早いうちに覚えて、使いこなせるようにしておきましょう。
②どこまで解けるようにすればいいのか?
次に、同時進行で基礎レベルの問題の演習も徹底しましょう。
学校の教科書レベルの問題です。
入試問題にも基礎レベルの問題が含まれていることがあります。
上位校でも学部を選べば、基礎問題を中心に構成されていることもあります。

まずは基礎レベルの問題の徹底
例えば、難関と言われる早稲田でも、
文化構想学部の日本史などは、教科書レベルを押さえていれば、高得点が狙えます。
また、基本問題で点数が狙えることはもちろん、応用問題の答えにたどり着くためには、基本問題で答えを出せる必要があります。
高2の冬までに、学校ですでに習っている内容は全て押さえておきましょう。また、教科書をしっかり解けるようになることはもちろん、問題集などでしっかり演習して復習することも忘れないでください。
高3の夏休みから過去問対策を始められることが理想です。
③「マーク式」、「記述式」どちらの対策が優先?
最後に、高2の1月は、必ず記述の練習をしましょう。
なぜなら、記述はあとから、勉強しようとしても取り返しがつかないからです。受験勉強の最初、もしくは前半にマーク形式で解く練習をしてしまうと、なかなか記述を書けるようになりません。

マークのテクニックや解き方を覚えてしまい、順序立てて説明する解き方をすることが難しくなるからです。
また、この時期はまだまだ志望校を変える可能性があります。現在の志望校がマーク式だからと言って、マーク式の練習だけで大丈夫、ということも避けましょう。
それに加えて記述式の練習をすることで、学習内容を深く理解することができるようになります。早稲田・慶應・上智・GMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)などの上位私立大学では、マーク式でも選択肢の違いは細かいことであることが多いです。
例えば、古文の解釈文を選ぶ問題では、間違えている選択肢でも一語分の訳以外は正しい文だということもあります。そのため、記述できるだけ深く内容を理解していれば、マークにも記述にも対応できるようになるのです。
いかがでしたでしょうか。
これが1月に勉強すべきポイントです。
とは言え具体的にはどうしたらいいか分からないという人も大勢いらっしゃいますよね。
そこで、主要3科目での学習内容をお話しします。
3.科目別対策(英・数・国)
科目別対策 英語編
英語の学習としては最低限、受験レベルの英単語帳を一周しておきましょう。
全て暗記しているというよりも、学校の単語テストで満点をとり続けている、というレベルが高2の冬では求められています。

ただ数日で何百単語覚えました!というよりも、毎日コツコツ●●語ずつ覚えました!の方が暗記できるのは当然のことです。
例えば、1日10単語ずつ覚えても、夏までに2000語以上覚えられます。
しっかり確実に、コツコツと単語は覚えましょう。
同じように、文法の内容も一通り学習しきっておく必要があります。
一冊の文法書を1周はやりきっておきましょう。
また、短めの長文も毎日1~2題は演習しましょう。
確実に力になります。
科目別対策 数学編
数学は、文系・理系問わず数ⅡBまで学校で使っているテキストを一周やりきっておきましょう。
理系ですと、もう数ⅡBの記述は問題ない、と言えるレベルにまでしておくと安心です。
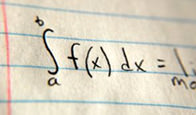
文系も数ⅠAの記述は完璧で、数ⅡBも教科書の問題(章末問題は除く)は解けるところまで勉強しましょう。
もちろん、公式は全て覚えていることが前提です。
科目別対策 国語編
国語では、高校の漢字テストは常に満点をとれるようにしておきましょう。漢字テストがない場合には、常用漢字集で1日10ずつ覚えていきましょう。

また、高2の1月の段階では、定期テストでも漢字と文学史だけは満点を必ずとれるレベルになっておく必要があります。
学校によっては、文学史をテストに出さないことも多いのですが、そういう学校に通っている高2生は、『国語便覧』を一周して、筆者作者と作品名が言えるようしましょう。
また、現代文の演習は短めの文を使い、週に2.3問は行いましょう。
いかがでしたでしょうか。
以上が、私大受験で勝てる高2の1月の勉強法です。
受験勉強をどうしようか、ぼんやり考えていた人は、その量にびっくりしたかもしれません。
ただ、毎年、早稲田・慶應・上智・GMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)などの上位私立大学に合格する受験生は、この時期から、こういった受験対策を、計画的に進めてきました。
とは言え、
「これから具体的に何をしていいかわからない」
「予備校や学校の対策だけでは不安」
「集団授業ではなく、自分のペースで勉強したい」
という方は、家庭教師を選ぶのも一つの手です。
家庭教師であればマンツーマン指導で、現在の学習状況、偏差値(成績)性格やペースに合わせた受験指導が可能だからです。
もし家庭教師が気になった方はぜひ以下のページもご覧ください。