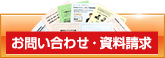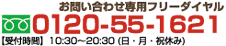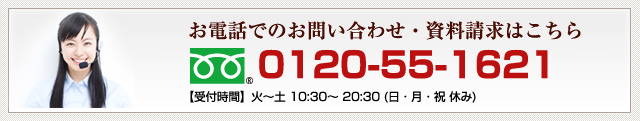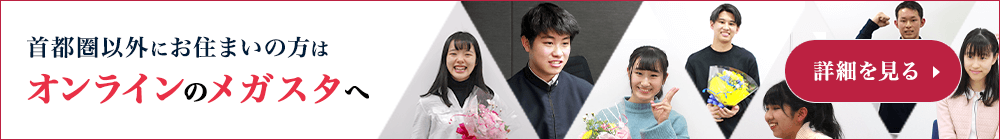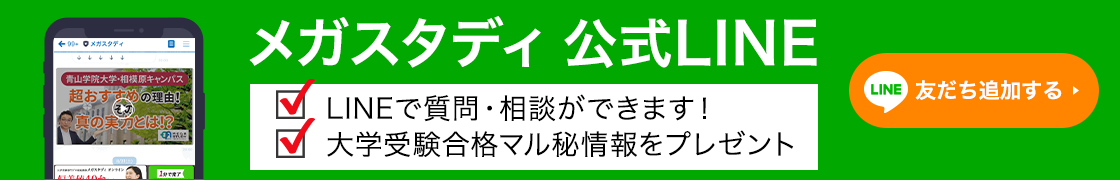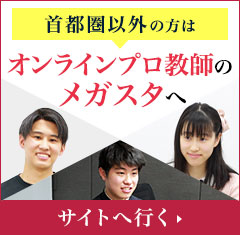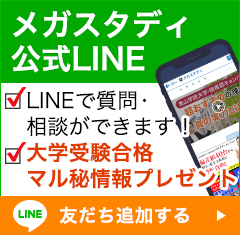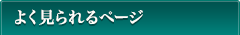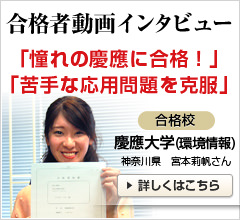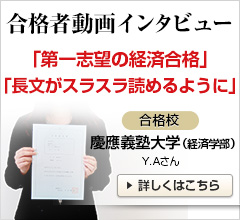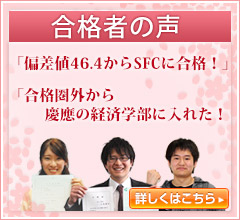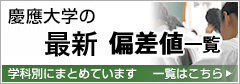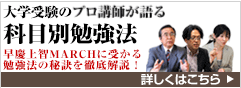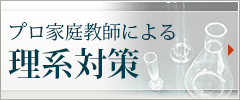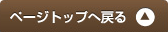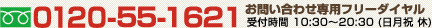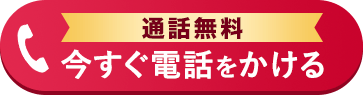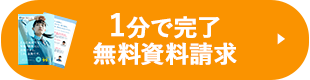慶應義塾大学
法学部
小論文 入試傾向と対策ポイント
偏差値40から慶應義塾大学に合格させます!
私大受験専門・家庭教師メガスタディが入試傾向を徹底解説!

このページでは、慶應義塾大学 法学部の小論文入試問題の「傾向と対策ポイント」を解説しています。
慶應義塾大学の法学部を目指す方には小論文入試の合格のヒントがきっとありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
入試傾向
試験時間90分、大問数1題、課題文3000~4000字、論述量1000字程度
年度によって、「筆者の見解の要約」「意見論述」の字数が指定されていることもある
理解力、構成力、発想力、表現力が求められる
法学部系統の専門領域に関わるもの
法・権利・政治に関する近年の議論を踏まえた出題になります。
現代社会に関する問題意識
現在の社会・政治のあり方への関心が問われています。
対策
法学・政治学の基礎知識は必須
前述の通り、慶應義塾大学法学部の論述力では、法学・政治学の基礎知識が必要になります。法学・政治学の基礎知識がないと、中身の濃い文章を書くことができません。説得性のある文章を書くには、ある程度の語彙力と法学・政治学の基礎知識を身につけることが大切です。
基礎知識習得のためには、普段から論説文や新聞の社会・文化・国際関係の記事に目を通すようにしましょう。しかし、具体的に何に目を通せば良いのかの判断は、受験生一人では難しいこともあります。慶應義塾大学法学部の論述力に詳しい人であれば、何を読んでおけば論述の役に立つかを知っています。必要な記事や論説文を的確にピックアップすることができるので、いざという時は、慶應義塾大学法学部の論述力の傾向に熟知している人の手を借りると良いでしょう。
評価のポイント
慶應義塾大学法学部の論述力では、試験に明記されている通り、次の4点が評価対象になります。
- 理解力:読解資料をどの程度理解しているか
- 構成力:理解に基づく自己の所見をどのように論理的に構成するか
- 発想力:論述の中に、どのように個性的・独創的発想が盛り込まれているか
- 表現力:表現がどの程度正確、かつ豊かであるか
これら4点で評価が受けられる論述展開をすることが、合格のカギを握ります。 それでは、この4点一つ一つについて、評価をもらうための対策をご紹介します。
課題文を十分に読みこなすためには
まず1点目の理解力ですが、これは課題文をどれだけ正確に読み取れているかが見られます。課題文をきちん読解できていないと、的を射た意見論述が出来ないので、課題文の読解は非常に重要です。
しかし、課題文は、決して読みやすい文章ではありません。論理的で専門性のある内容になっているので、そういった文章を把握する力を身につけておくことが大切になります。評論文や随筆文など、筆者の意見が書かれるジャンルの文章を多く読み、論理的な文章を読み解く練習をしていきましょう。
筆者の主張や意見に着目し、どのように論を展開しているかを骨組みで捉えられるようになるとベストです。筆者の主張・意見に下線を引いたり、色を塗ったりなどして、視覚的に読み解いてみるのもオススメです。
その際、筆者の主張・意見の論拠となる部分、主張・意見を補強するための具体例なども見つけられると、さらに理解力が向上します。
骨組み(プロット)を決める
次に、構成力ですが、これは、自分の意見・主張をいかに展開しているかが見られます。論の展開の仕方によって、同じことを言っていても、説得性がなくなってしまったり、説得性が強まったりします。ポイントは、説得性のある論を展開することです。そのためには、自分の考えをどの順序で述べるか、論拠や例を示すタイミングなどを細かく考えていかなくてはいけません。
ですから、書き始める前に、自分が論述するべき内容・ポイントを箇条書きで書き出す癖をつけることが重要です。論述を構成する要素を全て書き出した上で、どのように論を展開していくかを考えましょう。次に、論を並べる順番や、例を出すタイミングなどを組み替え、論述の道筋を作ります。これをプロット(骨組)と言います。 意見論述をするときには、必ずこのプロット(骨組)を決めてから、書き始めるようにしないといけません。最初は、プロットだけを作る練習をするのも一つの手です。
読み手をいかに説得させるか、よく考えてプロットを構成しましょう。ただ、プロットが説得性のあるものになっているかどうかを、自分で客観的に判断するのは難しいと言えます。慶應義塾大学・法学部が好む解答というのもあるので、一般的な論述の仕方で合格点が取れるとも限りません。慶應義塾大学・法学部の論述力の傾向に詳しい人に、添削を受け、ブラッシュアップしていくのがベストです。
既出の意見を焼き直すのはNG
3つ目に発想力です。意見論述には、ある程度のオリジナリティが求められます。どこかで聞いたことのある意見の焼き直しでは、高得点は望めません。個性的・独創的な要素を盛り込む必要があります。
そのためには、豊富な経験と知識が必要になってきます。経験をこの論述のために飛躍的に増やすことはできませんが、知識であればいくらでも蓄積することが可能です。ですから、法学部系統の学問の入門書、社会科学系の新書、古典的な著作などを読んで、できるだけ知識を補強するようにしましょう。特に、政治思想と法哲学の入門書は必読です。取り入れた知識は、知識としてただ覚えるのではなく、現実の社会と関連づけて考えられるレベルまで持っていくことが大切です。
また、法学部では現代社会の問題や国際関係に関する問題も出題されているので、現代社会と法との関係についてコンパクトにまとめられた参考図書にも目を通してみましょう。『法哲学講義』(東京大学出版会)、『法の臨界』(東京大学出版会)、『考える「時事問題」厳選60』(早稲田経営出版)などがオススメです。法学部を目指すのであれば、慶應大学法学部に限らず、一度は目を通してもらいたい書籍です。
手っ取り早く知識を増やすには、この論述力の傾向に詳しい人に、知識を補ってもらうのも手です。入試まで残り期間が少ないときは、あらかじめ押さえるべき重要ポイントを洗い出してもらい、効率良く吸収していくようにしましょう。
文末表現まで気を配る
表現力は、自分の考えを読み手に分かりやすく伝える力です。いくら意見を固め、論を展開する順序を決めても、最後の表現する段階で、上手く言葉を操れなければ読み手に伝えることができません。
接続詞の使い方、文末表現など基本的な部分から、文章表現を見直してみましょう。 文学的な比喩表現などを学んだり用いたりする必要はありませんが、法学・政治学の基礎知識や専門用語は必要になってきます。もちろん、専門用語に限らず、ある程度の語彙力も求められます。
専門知識・用語および語彙力を増やすためにも、論説文や新聞の社会・文化・国際関係の記事などを普段から読むことが大切です。知らない単語が出てきたら、逐一調べて暗記しようとするよりも、たくさんの文章を読むことをお勧めします。文章を読んでいるうちに、語彙力は自然と増えますし、文脈の中での単語の使い方もつかむことができます。
自分が気になった表現、単語、論展開の仕方などは、メモをとったり線を引いたりして、後から見直せるようにしておくと良いでしょう。
「要約→意見論述」を繰り返す
以上のように、4点すべてを念頭に入れて対策し、最終的には4点全てを合わせて意見論述ができるようにしなくてはいけません。そのためには、演習が不可欠です。 小論文などの演習も効果的ですが、「新書の1章を読んだら、その内容を400字にまとめる」という要約練習も効果的な対策です。
要約練習を十分に行った後は、その内容に関して、自分の意見を600字程度で述べてみましょう。頭の中で考えるのではなく、実際に書き出して、意見論述を完成させることが、力をつけるコツです。 こうした練習の積み重ねが、論述力を伸ばしていきます。ただ、解答を見ての自己採点では、書かなくてはいけないポイント、書かなくても良いポイントが、正確に判断できません。文章の見せ方や、論展開の工夫も、自分一人でブラッシュアップしていくのは難しいものです。
解答が一つに決まらない、論述力のような性格のものこそ、プロの手が必要になってきます。ですから、論述力の傾向に詳しい人の添削を受けるのが、合格への最短ルートです。そうでなくても、添削は必ず第三者にしてもらうようにしましょう。
まずは無料の資料請求、学習相談を
家庭教師のメガスタディには、慶應義塾大学・法学部に高い合格実績を出しているトッププロ家庭教師が多数在籍しています。
少しでもご興味をお持ちいただいた方は、まずは合格に役立つノウハウや情報を、詰め込んだ無料の資料をご請求ください。お急ぎの方はお電話ください。
また、慶應義塾大学・法学部に詳しい教務スタッフによる無料の学習相談も承っています。学習状況を伺った上で、残りの期間でどうやって受かるかをご提案いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。
◀ 慶應義塾大学法学部の他の教科も確認する